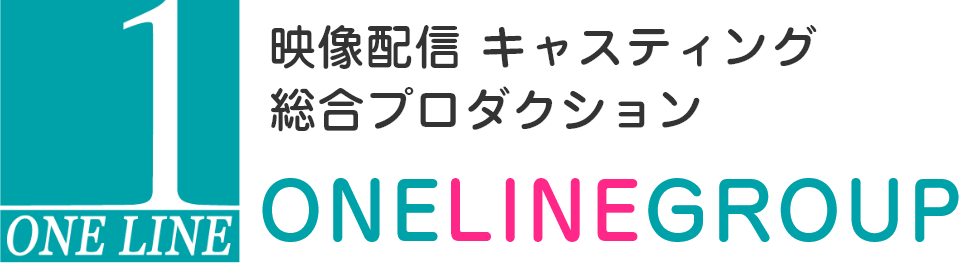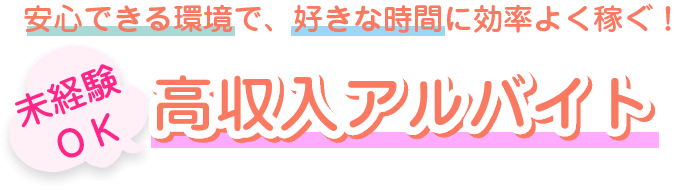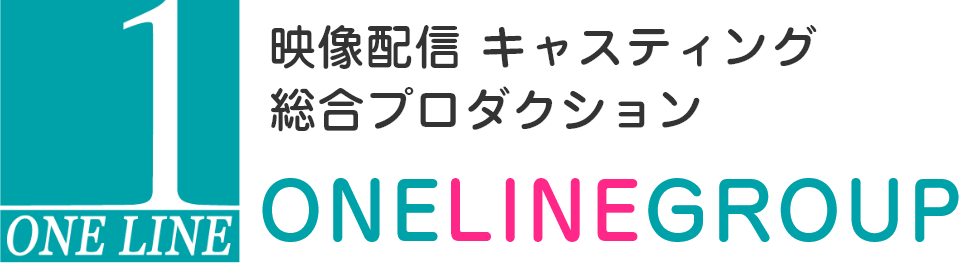現代においてSNSはただのコミュニケーションツールではなくビジネスにおいても多大な影響を及ぼす世界共通の文化として根付いています。
人同士のつながりやコミュニティの形成などが容易な反面、『誰でも気軽に見られる』というオープンな仕様で起こるトラブルも後を絶ちません。
今回のコラムでは改めてSNSの注意点や落とし穴などをわかりやすく解説してみたいと思います。
1.過度な承認欲求が生むトラブル
SNSの大きな魅力は『リアクションがつく事』に尽きます。
自分の投稿が知り合いの枠を超えて『いいね』が付くと嬉しいし、それだけでその瞬間を一緒に共有できる嬉しさがある反面、反応が増えてくると『もっと評価されたい』や、『ウケのいい投稿をしなくちゃ』と無意識に自分を演出し始める現象が起きがちです。
現実と投稿内容にギャップが生まれ、SNS専用の人格形成がなされることもしばしば…
さらには『誰もしていない事をしよう』と無意識に犯罪的な行動に手を染めてしまうことも過去の事例で何件も起きています。
2.見ず知らずの誰かと比較してしまいコンプレックスに…
SNSを開けば誰かが海外旅行に行き、誰かが恋人と幸せそうにしていて、誰かが昇進を報告しています。そんな見ず知らずの日常が並んでいると、つもりがなくても無意識に比較してしまいがちです。
これらは一見リアルに見えて『演出された一場面』である事も多いです。
実際には誰もが悩みや葛藤を抱えています。しかし、SNSにおいてはネガティブな感情は見えづらく、他人と自分を無意識に比較して自己否定に陥るケースも年々増加しています。
それはその人にとって見せたい瞬間の切り取りにしかすぎません。表面だけの情報で比較してしまうといらぬコンプレックスを抱いてしまいます。
メンタルヘルスを保つためには、他者の情報を『全体』ではなく『断片』として受け止める冷静さがSNSとうまく付き合う秘訣となります。
3.その情報、本当に正しい?
SNSは情報伝達のスピードが極めて高く、拡散性に秀でたツールですが
その拡散力の裏側には『確認されてない情報』が流通してしまう危険性も孕んでいます。
一例として、災害時に誤情報が拡散され、混乱や不安を助長した事例など
一部の愉快犯による拡散の危険性やリスクも念頭に入れなければなりません。
情報の真偽を確かめずに共有することは、悪気がなくてもデマの拡散に加担していることになりかねないので、情報発信者であると同時に、常に受け取り側でもあるという自覚がすべてのユーザーに求められています。
4.言葉の誤解と人間関係の摩擦
SNSは主にテキストでのコミュニケーションで成り立っています。
そのため、文脈や感情のニュアンスが伝わりづらく、時にはそれが原因でいらぬ誤解を生んでしまうことも…
例えば、何気ないツッコミのつもりで書いた一言が、相手には攻撃的に映ってしまい、関係に亀裂が入るといった事例は珍しくありません。
対面とは異なり、補足や表情がないからこそ、より慎重な言葉選びと相手の受け取り方を配慮する視点が重要です。
5.プライバシーの軽視と悪用のリスク
SNSに投稿された情報から、個人が特定されるリスクは想像以上に高いです。自宅周辺の風景や通学・通勤ルート、日々の行動パターンが投稿内容から読み取られ、悪意ある第三者に利用されたケースも報告されています。
特に小さい子供が居る場合は、子供の写真や学校名、日常的な位置情報を含む投稿は思わぬ犯罪の引き金となる可能性も含んでいます。
『誰が見てるかわからない』という前提に立ち、自身のプライバシーは自ら守る意識が求められます。
SNSにまつわる法律について
オープンな仕様が魅力的な各種SNSですが、当然法律の範囲内での利用をしなくてはなりません。
ここではつもりがなくても起きやすい法律違反などを例に挙げながら
SNSにまつわる法律について解説してみたいと思います。
1.名誉棄損・侮辱罪(刑法)
他人の名誉を傷つける投稿(たとえば「○○は詐欺師だ!」みたいな断定的な内容)は、名誉毀損に当たる場合があります。たとえそれが事実だとしても公然の場でそれを発言してしまうと名誉棄損にあたる場合があります。
侮辱罪は事実じゃなくても「バカ」「死ね」とかの暴言で成立することも。
社会的な評価を貶めるような表現で成立します。よくある『誹謗中傷』などはこれにあたる場合が多いです。
2.プライバシー権の侵害
本人の許可なく顔写真や、自宅住所、学校や勤務先などを投稿すると違法行為として取り締まられます。不特定多数が映り込むような繁華街での写真の撮影などは実はかなりリスクが高い行為ですので、細心の注意を払いながらの投稿を心がけましょう。
3.著作権違反
引用などの要件を満たさずに他者の描いたイラストや文章などをそのまま転載した場合、違法となります。『出典を書けばOK』は実は通用しません。
さらにそれを利用して商用などに使用した場合はさらに重い罰則となります。
4.不正アクセス禁止法違反
他者のSNSアカウントに無断でログインする行為が該当します。
IDやパスワードは必ず自己責任において厳重に管理する必要がありますので、無暗に他者に教えたり、特定されやすいIDやパスワードはなるべく避けるようにしましょう。
その他にも様々な法整備がされていますが、中でも起こりやすいものを抜粋して簡単にですが解説させて頂きました。
無意識に違反行為をしてしまっているケースも多くみられます。
『そんなつもりじゃないのに…』は罰則を受けてからでは遅いので投稿する前に本当に大丈夫か?と冷静に見返すことも大事です。
まとめ
SNSは私たちの生活を豊かにし、時には救いになるかもしれない存在です。
しかし、その便利さに依存し、評価に囚われすぎることで自分自身の軸を失う危険性も持ち合わせています。
情報の受信者・発信者としての責任、そして心の健康を守るためにも
適切な距離感で共存する意識が必要となります。
あくまでSNSは『使うもの』。
決して『支配されるもの』ではないので
今一度ネットリテラシーと向き合う意識が今後のSNSの発展のカギとなるでしょう。